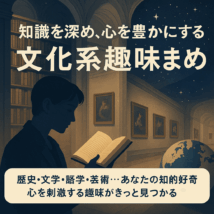1. はじめに
「せっかく趣味を始めたのに、いつの間にかやめてしまった……」そんな経験はありませんか?最初はワクワクして取り組んでいたのに、気づけば道具は押し入れに、アプリはアンインストール、SNSに投稿した“初日”の写真だけが残る──このようなケースは決して珍しくありません。
「自分には継続力がないのかも」「どうせ三日坊主になるし…」と、自信を失ってしまう方も多いでしょう。しかし、実際には“趣味が続かない理由”は個人の性格だけに起因するものではなく、環境・選び方・心理的ハードルなど、いくつもの要素が絡んでいます。つまり、理由がわかれば改善もできるということです。
趣味は、生活に潤いや刺激を与える大切なエッセンスです。没頭することでストレスが軽減されたり、新しい人間関係が生まれたり、思わぬ副業のチャンスにつながることさえあります。だからこそ「続く趣味」との出会いは、日常を少し豊かにする大きな一歩なのです。
この記事では、趣味が続かない主な原因を8つに分けて分析し、それぞれに対する“続けるための具体策”を解説していきます。「なぜ私はいつも続かないのか」「どんな趣味なら長続きするのか」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。次の趣味は、きっとあなたの人生を少し変えてくれるはずです。
2-1. 成長が見えず挫折するから
多くの人が趣味をやめてしまう原因のひとつが、「成長が感じられないことによる挫折」です。最初は「楽しそう」「やってみたい」という好奇心で始めたはずなのに、思ったように上達せず、「自分には向いていない」と感じてしまう。これはどんな趣味にも起こりうる、ごく自然な心理反応です。
たとえばギターを例に挙げると、コードの押さえ方やリズム感を身につけるには、ある程度の練習と時間が必要です。しかし最初の数週間で弾けるようになる曲は限られ、うまく弾けないことでモチベーションが下がることもあるでしょう。こうして「自分は不器用だ」と思い込み、途中でやめてしまうのです。
しかし、ここで注目すべきは「成長が“見えない”だけで、実際には進歩している」という点です。人は目に見える成果があると喜びや達成感を得やすい一方で、進歩が小さかったり自分で気づけなかったりすると、努力が無意味に思えてしまうのです。
この「見える化されていない成長」が、継続の大きな壁になります。
小さな成功を“見える化”する
この問題を解決するには、成長を「見える形で実感」できる仕組みを用意することが重要です。たとえば次のような方法があります。
- 日記や記録アプリで練習内容や成果を書き残す
- SNSやブログで進捗をシェアする(自己肯定感アップに効果的)
- 「今日はここまで」と決めた小さな目標を毎回設定する
- 初心者用テキストを順番にクリアするなど、達成感のある構造にする
このように、あらかじめ小さなステップを設定し、それをクリアしていくことで、自分自身の「できた!」を積み重ねることができます。これにより、モチベーションは維持され、成長実感も高まるため、挫折しにくくなります。
「成果」ではなく「変化」に目を向ける
また、「結果(成果)」ではなく、「変化(プロセス)」に目を向ける意識も大切です。たとえば、
- 「ギターの弦を張れるようになった」
- 「前より手が動くようになった」
- 「最初より指が痛くなくなった」
こうした小さな変化を楽しめるかどうかが、趣味の継続において大きなカギとなります。スキルそのものの向上だけでなく、自分の中に起きた心境の変化や体感の変化を受け止めることで、趣味との向き合い方がポジティブになります。
2-2. ハードルを自分で上げすぎている
趣味が続かない大きな原因の一つとして、「自分でハードルを高く設定してしまう」という心理的傾向があります。これは完璧主義の人に多く見られる傾向で、理想と現実のギャップに苦しみ、自分に失望してやめてしまうパターンです。
たとえば、絵を趣味にしたいと思った人が「プロのように描けるようになりたい」と強く思いすぎた結果、思うような作品が描けず「自分には才能がない」と結論づけてしまう。これは「うまくなりたい」というモチベーションが、逆にプレッシャーとして働いてしまう典型例です。
なぜ私たちはハードルを上げすぎてしまうのか?
このような思考には、以下のような心理的背景が隠れています。
- SNSで上手な人の作品を見て、無意識に比較してしまう
- 「せっかく始めるなら、しっかりやらなきゃ」と思う真面目さ
- 達成主義・結果主義的な教育や仕事経験の影響
こうした思考は、一見やる気の現れのようでいて、実は「継続」を阻む大きな壁になるのです。
続けるためのコツは「小さな成功の積み重ね」
高すぎる理想を掲げるよりも、「今日は5分だけ描いてみよう」「週に1回だけでもやってみよう」といった“小さな成功体験”を積み重ねていくことの方が、長期的には大きな成果につながります。
趣味においては、「頑張る」よりも「楽しむ」ことを優先すべきです。完璧にこだわるよりも、続けることそのものに価値を見出すマインドに切り替えることで、自分を追い詰めることなく趣味を続けられるようになります。
まずは「3回ルール」から始めてみよう
おすすめなのは、「3回ルール」です。まず3回試してみて、「やっぱり面白い」と思えたら続けてみる。「ちょっと違うな」と感じたら、無理に続けなくてもOK。初期段階では判断しきれないことが多いため、あらかじめ「評価は3回目以降にする」と決めておくと、気持ちが楽になります。
自分に合ったペースで、楽しみながら少しずつ続けることが、結果として「趣味が長続きする秘訣」となります。
2-3. 続けやすい趣味ではないから
趣味が続かない理由のひとつに、「そもそも続けやすい趣味ではなかった」という要因があります。つまり、興味はあるけれど現実的に続けにくい条件が揃っていた──というケースです。
たとえば、以下のような趣味はハードルが高く、挫折につながりやすくなります。
- 毎回遠出が必要(登山・サーフィンなど)
- 高額な初期費用や継続コストがかかる(楽器、ゴルフなど)
- 用意・片付けに時間がかかる(キャンプ、油絵など)
- 天候や季節に左右されやすい(釣り、天体観測など)
- 特別なスキルや資格が必要(陶芸、写真現像など)
もちろん、こうした趣味に魅力があるのは間違いありません。しかし、日常生活とのバランスを取りにくいと、せっかくの趣味が「義務化」や「ストレス」になってしまう可能性があります。
趣味は「ライフスタイルと合っているか」が鍵
大切なのは、「自分の生活リズムやライフスタイルに合った趣味かどうか」を考えることです。どんなに魅力的でも、時間・場所・お金・体力などの面で無理があると、継続は困難になります。
たとえば、週末に家族との時間を大切にしたい人が「毎週登山に行こう」と決めてしまうと、家族との調整が必要になり、次第にお互いにストレスを感じることもあるでしょう。
また、体力や健康状態に合っていない趣味も、継続しにくくなる一因です。運動不足を解消しようと始めたスポーツが、体力的についていけずに挫折した、という声もよく聞かれます。
続けやすい趣味とは?
では、どのような趣味が「続けやすい趣味」といえるのでしょうか。以下のような条件を満たすものは、継続しやすい傾向があります。
- 自宅でできる(例:読書、イラスト、動画編集、家庭菜園など)
- すぐに始められる(道具不要、または簡単に揃えられる)
- 小さな単位で楽しめる(5分・10分でもOK)
- 場所・時間に縛られない
- 続けること自体が癒しやリラックスになる
最初の一歩としては、こういった“低コスト・低ハードル”な趣味を選ぶことがおすすめです。「まずは気軽にやってみる」ことで、自分に合っているかどうかも見えてきます。
「好き」より「続けやすさ」で選ぶ視点も
趣味を選ぶとき、つい「興味がある」「やってみたい」といった“好き”の感情を優先しがちです。しかし実は、「続けやすさ」の視点から選んだほうが、結果的に楽しくなるケースも少なくありません。
「通いやすいジムだから続いた」「毎日5分だけでいいから英語アプリが続いてる」など、実際に続いたからこそ楽しさや上達を感じられるようになる、という流れです。
つまり、“続けられるから楽しくなる”という逆転の発想も、趣味選びでは非常に重要な観点なのです。
2-5. 自己否定や“こうあるべき”が邪魔をする
趣味が続かない背景には、実は「自分で自分を制限してしまっている」というケースも少なくありません。特に、強い自己否定や「趣味はこうあるべきだ」「この程度では意味がない」といった“理想像”に縛られてしまう人は、楽しさよりもプレッシャーを感じてしまい、結果的にやめてしまうのです。
「楽しいはずの趣味」が苦しくなる瞬間
たとえば、こんな思考に心当たりはないでしょうか?
- 「この程度の腕で趣味だなんて言えない」
- 「他の人はもっと上手くやっているのに、自分は…」
- 「毎日やらないと意味がないのでは?」
- 「成果がないと時間のムダかも」
これらの思考は、いわゆる“べき思考”や“完璧主義”が引き起こすもので、自分を肯定できず、「楽しむこと」が目的だったはずの趣味が、いつの間にか「評価されなければならない」「誰かに証明しなければならない」ものへと変わってしまうのです。
他人の目を気にしすぎると、趣味は続かない
SNSが当たり前の時代において、「発信すること」が趣味の一部になるケースも増えています。もちろん、それ自体は悪いことではありません。しかし、“いいね”の数や他人の評価を気にしすぎるあまり、「発信しないと意味がない」「うまくできなかったから投稿できない」と自分を否定してしまうと、次第に趣味そのものから遠ざかってしまうのです。
本来、趣味は「誰かのためにやる」ものではなく、「自分のために楽しむ」ものであるべきです。他人と比べる必要も、誰かに認められる必要もありません。
セルフコンパッションが継続の鍵
こうした自己否定を乗り越えるためには、「セルフコンパッション(自分に優しく接する力)」を意識することが効果的です。
セルフコンパッションとは、自分がミスをしたり、期待通りに進まなかったときに、「そんな日もあるよ」と自分を責めずに受け入れる力のこと。これは、習慣形成や継続力において非常に大きな役割を果たします。
たとえば、
- 「今日はやらなかったけど、それもOK」
- 「失敗したけど、そこから何か学べた」
- 「続いていない期間もあったけど、また再開できた自分を褒めよう」
こうした言葉を、自分に向けてかけてあげることができれば、趣味との向き合い方が大きく変わっていきます。
趣味に“理想像”はいらない
「趣味なんだから自由にやっていい」「上手くなくても楽しければそれで十分」──このマインドを持つことで、続けることへのハードルがぐっと下がります。
そもそも趣味とは、自己実現やストレス発散、好奇心の追求などを目的にしてよいものです。そこに“義務”や“義理”のような感覚を持ち込むと、本来の楽しさが薄れてしまいます。
大切なのは、「楽しんでいる自分を認めること」。自分のペース、自分の形で、無理なく続ける。それが、長く愛せる趣味につながっていくのです。
2-6. 健康・メンタルの影響で趣味に集中できない
「やりたい気持ちはあるのに、なぜか手が動かない」「何をしても楽しめない」と感じたことはありませんか?これは、決して“やる気がない”からではありません。実は、趣味が続かない背景には、身体的・精神的なコンディションの乱れが関係していることも多いのです。
私たちの集中力や意欲は、心身の健康と密接に関わっています。疲れが溜まっていたり、睡眠不足が続いていたり、ストレスを抱えていたりすると、本来は楽しいはずの趣味にも気持ちが向かなくなってしまいます。
「趣味ができない自分」を責めないで
「続けられない自分はダメだ」と自己嫌悪に陥る人は少なくありません。しかし、まず知っておいてほしいのは、趣味は“元気があるときに楽しむもの”だということ。心や身体が消耗しているときに、「趣味をやらなければ」と無理に行動しようとしても、逆にストレスになることさえあります。
特に、うつ傾向や自律神経の乱れがあるときは、意欲が極端に下がり、普段なら楽しめることにも興味が持てなくなるものです。この状態は意志や性格の問題ではなく、脳やホルモンの働きによるもので、誰にでも起こり得ます。
だからこそ、「趣味を再開できない=自分が悪い」という思考を手放すことが、回復への第一歩になります。
マズローの欲求5段階から考える「趣味の優先度」
心理学者マズローは、人間の欲求を5段階に分けて理論化しました。
- 生理的欲求(食事・睡眠など)
- 安全の欲求(健康・経済の安定など)
- 社会的欲求(人間関係・所属)
- 承認欲求(他人からの評価、自尊心)
- 自己実現の欲求(創造性、成長)
趣味は5段階のうち「自己実現」の領域に位置しています。つまり、下位の欲求(睡眠・食事・安全など)が満たされていなければ、趣味を心から楽しむことは難しいのです。
調子が悪いときほど、まずは「寝る」「休む」「栄養をとる」といった基本的なことに意識を向けてください。趣味を再開するのは、それらが整ってからで大丈夫です。
小さな“癒しの習慣”から再スタートを
心や身体が疲れているときは、趣味を「がっつり楽しむ」必要はありません。むしろ、負担にならない範囲での“癒し”として取り入れるのがおすすめです。
たとえば、
- 静かな音楽を聴きながら塗り絵をする
- お香やアロマを焚いて5分だけ読書する
- 朝に1ページだけ日記を書く
- 観葉植物に水をあげる
こうした「行動に意味を求めすぎず、ただ心地よさを感じられる」行為が、趣味への回帰をスムーズにしてくれます。
心身のコンディションを受け入れることが“継続”の第一歩
健康状態や心の調子は日によって変わるもの。趣味ができない日も、調子が悪い時期も、「そういう時期なんだな」と受け止めてみてください。そして少し元気が出たときに、また趣味に戻ればいい。それで十分なのです。
無理をせず、自分を責めず、自然なペースで向き合うこと。それが、趣味を長く続けていくための土台になります。
2-7. 集中力が妨げられている(スマホなど)
「趣味を始めたのに、なぜか集中できない」「気づいたらスマホをいじっていて、全然進んでいない」──このような悩みは、現代ならではの“デジタル環境”が大きく関係しています。
スマートフォンやSNS、動画配信サービス、通知の多いアプリなど、私たちは常に情報の波にさらされながら生活しています。その結果、「集中力が持続しない」「物事に没頭できない」という状態になりやすくなっているのです。
なぜ集中できないのか? 脳の仕組みから考える
人間の脳は、基本的に“刺激”に反応しやすい構造をしています。スマホの通知音や新しいメッセージ、SNSの更新情報などは、脳にとって「快」の刺激であり、注意をそちらに奪われやすくなるのです。
たとえば、趣味として読書や手芸、イラストに取り組んでいても、スマホの通知が鳴った瞬間に集中が切れてしまう。しかも、そのあと元の集中状態に戻るには平均で20分近くかかるとも言われています。これでは「趣味の時間=なんとなく過ぎていく時間」になってしまい、やがて「意味がない」と感じてやめてしまう原因にもなりかねません。
デジタル環境と趣味の“相性”を見直そう
現代では、スマホやパソコンを使う趣味(例:動画編集・写真加工・デジタルイラスト)も多いため、「完全にデジタルを排除する」というのは現実的ではありません。だからこそ重要なのは、「集中しやすい環境を意図的に作ること」です。
集中を妨げないために、次のような工夫が有効です:
- 作業中は通知をオフにする/機内モードにする
- スマホは別の部屋や引き出しに置く
- タイマーを使って“時間を区切る”
- アプリやSNSをブロックするツールを導入する
- 紙とペンなど、アナログな道具でできる趣味を選ぶ
とくに、15〜30分ほどを1ブロックとして集中する「ポモドーロ・テクニック」などは、趣味を習慣化するうえで非常に効果的です。
「ながら趣味」はリラックス用、「没頭趣味」は集中力育成に
集中力を育てる趣味と、リラックスのために気軽に楽しむ趣味は別モノとして考えると、気持ちの切り替えがしやすくなります。
たとえば、
- テレビを見ながら編み物をする → リラックス用の「ながら趣味」
- 静かな環境で写経をする → 集中力を高める「没頭趣味」
このように、目的や気分に応じて使い分けると、「集中できない=趣味が続かない」という誤解に陥らず、自分に合ったスタイルを模索できるようになります。
“集中力は訓練できる”と知ろう
集中力は生まれつきの才能ではなく、繰り返しの習慣によって鍛えることができます。最初は5分だけでもよいのです。「決めた時間だけスマホを触らない」「今日だけは本に集中してみる」といった小さな意識づけが、やがて習慣を生みます。
趣味を楽しむ時間は、情報社会における“デジタルデトックス”にもつながります。画面の向こう側ではなく、いま目の前にあることに意識を向ける時間を意図的に持つ。それが、日々の生活の質を高め、趣味を長く楽しむ土台になるのです。
2-8. 他者承認や収益に依存しすぎている
「趣味を通じて“何か成果を出したい”」「人から褒められたい」「お金につながらなければ意味がない」──このような考えが強くなると、趣味は一気に“義務”や“ストレス”へと変わってしまいます。
SNS全盛の現代において、私たちは知らず知らずのうちに「他者の評価」を気にするようになっています。InstagramやX(旧Twitter)などで作品や成果を公開し、「いいね」や反応があると嬉しい反面、反応が少なければ「自分はダメかも」「続ける意味があるのかな」と不安になる。そんな心理状態に陥った経験がある方も多いのではないでしょうか。
「承認欲求」は自然な感情、でも…
人は誰しも、認められたいという気持ち=「承認欲求」を持っています。これ自体はごく自然で健全な欲求です。しかし、この欲求が強くなりすぎると、自分の内側にある“楽しさ”よりも、外からの“評価”ばかりを気にするようになります。
たとえば、
- 絵を描くのは楽しかったのに、フォロワーが増えないことで自信を失う
- 写真を投稿しても反応が薄く、「もうやめようかな」と思ってしまう
- ブログを書いていたが、収益が出ないのでモチベーションが下がる
これらはすべて「他者からの承認」や「経済的リターン」に依存してしまった結果、趣味の本来の目的を見失ってしまったパターンです。
「好き」を見失うと続かない
他者の評価やお金を目的にしすぎると、自分が「なぜこれをやっていたのか?」という根本的な“好き”の気持ちが薄れていきます。そして、それが感じられなくなった瞬間、続ける理由がなくなってしまうのです。
たとえば、もともとは「自分の感性を表現したい」と始めたイラストが、「バズらないと意味がない」「ファンがつかないと価値がない」という思考にすり替わってしまったとき、それはもはや趣味というより、義務に近い状態です。
結果的に、“疲れてしまう”“やめたくなる”のは当然のことなのです。
内発的動機に立ち返ることがカギ
長く続けられる趣味は、「自分の内側から湧き出る楽しさ」が原動力となっています。これを心理学では「内発的動機」と呼びます。
内発的動機の例:
- 楽器を演奏すると気分がスッキリするから
- 写真を撮ると自然との一体感を感じられるから
- 文章を書くと自分の思考が整理されるから
こうした“純粋な動機”がある趣味は、他者からの評価があってもなくても、自分の中で満足感や達成感が得られるため、長続きしやすくなります。
「発信しない趣味」もあっていい
今の時代、「何でもシェアしなきゃ」という空気がありますが、趣味は必ずしも発信する必要はありません。
- 誰にも見せないスケッチブック
- 自分のためだけに撮る写真
- 書き溜めている非公開の日記
こうした“誰のためでもない趣味”は、他人の評価に左右されることなく、自分だけのペースで楽しめるという点で、とても貴重です。
もちろん、発信したい人はしても構いません。ただ、「評価があるから続けられる」のではなく、「楽しいから続けたい」と思える状態を大切にしてほしいのです。
お金に換えなくてもいい
副業ブームの影響で、「趣味は収益化できなきゃ意味がない」と感じる人も増えていますが、それもひとつの幻想です。収益を目指すと、趣味が“作業”や“仕事”に変わり、本来の楽しみ方が失われてしまうことがあります。
「稼げるかどうか」よりも、「自分の心が満たされるかどうか」で趣味の価値を判断することが、長く続けるためのポイントです。
3-1. 自分の“ディープドライバー”を知る
趣味を続けられる人には、ある共通点があります。それは「自分がなぜその趣味をやっているのか」が明確であるということです。なんとなく面白そうだから始める人ももちろん多いですが、長く継続している人ほど、自分の中にある深い動機──いわば“ディープドライバー”を意識的または無意識的に理解しています。
ディープドライバーとは、「その行動をすることでどんな気持ちを得たいのか?」という内面的な欲求のこと。たとえば、以下のような動機が挙げられます。
- 心を落ち着けたいから → 書道やガーデニング
- 自己表現をしたいから → 絵画や小説
- 成長を感じたいから → 楽器演奏や語学学習
- 人とつながりたいから → ボードゲームやダンス
- 感性を刺激したいから → 写真や音楽鑑賞
これらの欲求は、必ずしも他人には見えません。しかし、本人にとっては非常に強い原動力になります。だからこそ、趣味を始める前や、途中で迷いが生じたときには「自分がこの趣味で得たいものは何か?」と問い直すことがとても大切です。
では、ディープドライバーを見つけるにはどうすればいいのでしょうか。おすすめの方法は、以下の3ステップです。
ステップ①:憧れの人や状況を思い浮かべる
「こんな生活に憧れる」「この人の趣味の姿勢が好き」──そんな人物やイメージがあれば、それはあなたの内面にある価値観を映しています。たとえば、自然の中で静かに読書をしている人に憧れるなら、「静けさ」や「内省」が自分にとって大事なのかもしれません。
ステップ②:過去の経験からヒントを得る
子どものころに夢中になったことや、楽しかった活動を思い出してみてください。そこには、あなたがもともと持っていた“好きの種”が眠っている可能性があります。
ステップ③:「〜したいから」を繰り返す
たとえば「写真を始めたいから」→「記録が残せるから」→「思い出を形にしたいから」→「人生を大切にしたいから」……と、自分に問いかけを続けていくと、本質的な欲求が見えてきます。
このように、自分のディープドライバーを言語化しておくことで、趣味に対するブレが減り、多少気持ちが揺れたときでも「やっぱりこれは自分にとって大切だ」と思い直せるようになります。
他人からの評価や流行に左右されず、「自分のためにやっている」という確信があれば、趣味は自然と続いていきます。逆に、動機が曖昧なままだと、モチベーションは失われやすく、少しのつまずきで「やっぱり向いてない」と感じてしまうことも。
だからこそ、趣味選びの第一歩として「なぜこれをやりたいのか?」という深い問いかけを、自分自身にしてみてください。
3-2. 小さなステップで始める
趣味を始めるとき、多くの人が「ちゃんとやらなきゃ」「成果を出したい」といった気持ちを強く持ちがちです。たとえば、「英語を学ぶなら毎日30分は勉強しなきゃ」「ギターを始めるなら最初に一式そろえないと」など、完璧なスタートを目指してしまいます。
しかし、この“高い目標設定”こそが、趣味が続かなくなる最大の落とし穴のひとつです。
実際に趣味を長く続けている人の多くは、始まりがとてもささやかだったりします。最初は「ちょっと面白そうだから」「気分転換になればいいな」くらいの軽い気持ちで、小さな行動から始めています。
なぜ“小さく始める”と続けられるのか?
その理由は大きく2つあります。
- 心理的ハードルが低くなるから
大きな目標や準備が必要な趣味は、「やるぞ」と気合いを入れないと始められません。すると、少し疲れていたり気分が乗らないときに「今日はいいや」となってしまい、だんだん間隔が空き、やがてやめてしまうのです。 - 成功体験を積みやすいから
「今日もできた」という感覚は、趣味を習慣化するうえでとても重要です。小さなステップなら、達成感を感じやすく、自信にもつながります。
「最低限の一歩」でいい
では、具体的にどのように始めればよいのでしょうか。おすすめは、“これなら今日でもできる”というレベルまで行動を分解してしまうことです。
たとえば:
- ランニング → 外に出て、靴を履くだけ
- 英語学習 → 単語アプリで1単語だけ覚える
- 読書 → 1ページだけ読む
- イラスト → 1本の線を描いて終わってもOK
このように「ハードルを徹底的に下げる」ことで、“できた”という体験を毎日積み上げることができます。続けているうちに自然と時間も伸び、クオリティも上がっていくのです。
「スモールスタート+習慣化」が最強の組み合わせ
スタンフォード大学の行動科学者BJ・フォッグが提唱する「Tiny Habits(小さな習慣)」でも、習慣形成には“超小さな行動”から始めることが重要とされています。
この理論によると、行動の習慣化には3つの条件が必要です:
- 簡単すぎる行動から始めること
- 特定のタイミングに紐づけること(例:朝食後に1分間)
- 達成後に自分を褒めること(例:よくやった!と声に出す)
この3つを意識することで、趣味が日常生活に溶け込みやすくなり、モチベーションがなくても“気づいたら続いている”状態がつくれるようになります。
「1%の進歩」で十分
「趣味だから気軽に続けたい」「でも、やるからにはうまくなりたい」──そんな人に伝えたいのが、“1%の進歩”で十分という考え方です。
たとえば、週に1回30分でも、1年間で約26時間の積み重ねになります。仮に始めたばかりの人が、1年後に26時間分の経験を積んでいれば、きっと「それなりにできる自分」になっているはずです。
目標は高くてもいい。でも、最初の一歩は“笑えるほど小さく”していい。大切なのは、完璧なスタートより「まず動くこと」、そして「またやってみよう」と思える習慣をつくることなのです。
3-3. 時間・お金・場所のハードルを下げる
趣味が続くかどうかを分ける大きな要因のひとつが、「どれだけ気軽に取り組めるか」です。始めるには高価な道具が必要、まとまった時間がないとできない、特別な場所に出かけないといけない──こうした“環境面のハードル”は、趣味を遠ざけてしまう原因になりがちです。
逆に言えば、「時間」「お金」「場所」の3つの負担をできるだけ下げることができれば、趣味はグッと継続しやすくなります。
なぜ“ハードルの低さ”が大切なのか?
趣味に対するモチベーションは、常に高い状態が続くわけではありません。疲れている日、気分が乗らない日、仕事が立て込んでいる日……そんなときでも「ちょっとだけならできるかも」と思える状態であれば、途切れずに続けられます。
たとえば、以下のような趣味は継続しやすい傾向があります。
- 家の中で完結できる(読書、イラスト、手芸など)
- 1回数百円〜数千円以内で楽しめる
- 道具を出すのが簡単 or 常に出しっぱなしでいい
- 5〜10分程度でも満足感を得られる
一方、道具を揃えるのに数万円、準備と片付けに毎回30分以上、交通費や移動時間がかかる──このような趣味は、「また今度でいいか」と後回しになり、結果として続かなくなるケースが多いです。
実行コストを下げる工夫あれこれ
ここでは、趣味を継続しやすくするための“実行コストを下げるアイデア”をご紹介します。
■ 時間のハードルを下げる
- 「朝食後の5分」「通勤中の10分」など、スキマ時間にできる趣味を選ぶ
- 毎日でなくてもよいと最初から決めておく(例:週末だけ)
■ お金のハードルを下げる
- 道具は100円ショップやリサイクルショップで揃える
- 無料アプリやYouTubeで学べる趣味から始める
- レンタル・サブスク(楽器、カメラなど)を活用する
■ 場所のハードルを下げる
- 自宅でできる趣味を優先的に選ぶ
- 外出が必要な場合でも、徒歩圏内や生活動線の中で完結するようにする
- オンラインでも完結する趣味を検討する(語学、プログラミング、動画編集など)
“趣味環境の最適化”は立派な習慣化戦略
「環境が整っていれば人は行動しやすくなる」というのは、習慣形成における有名な心理学的原則です。つまり、気軽に始められて、途中で中断されにくいような環境を作ることは、モチベーション以上に大切です。
たとえば、
- 道具はすぐ手に取れる場所に置く
- 趣味用のスペース(机の一角、収納ボックスなど)をつくる
- “ながら”でできる趣味(音楽を聴きながらストレッチなど)を取り入れる
このように、自然と趣味に手が伸びる状況をつくっておけば、疲れている日でも“ゼロにはならない”行動がとれるようになります。
「できるようになったら…」より「今の自分に合っているか」
「子育てが落ち着いたら」「時間に余裕ができたら」と、将来の理想的な自分を想定して趣味を選ぶ人も少なくありません。ですが、それよりも大事なのは、「今の自分が無理なく楽しめるかどうか」です。
生活スタイルや気力体力に合っていなければ、どんなに魅力的な趣味でも続けることは難しくなります。無理をせず、“日常の中で無理なく続けられること”を大切にしてみてください。
3-4. 仲間をつくる・コミュニティに参加する
趣味を長く続けるために効果的な方法のひとつが、「一緒に楽しむ仲間を持つこと」です。人は誰かと関わることでやる気が高まり、継続するための外的なきっかけも生まれやすくなります。
一人で始めた趣味でも、気づけば仲間ができていた──というケースは少なくありません。むしろ、長く続けている人の多くが、趣味を通じて“ゆるくつながれる場”を上手に活用しています。
なぜ「仲間」がいると続くのか?
仲間やコミュニティがあると、以下のような効果が期待できます:
- 共通の話題ができて楽しい
- 相手に報告・共有することでモチベーションが上がる
- ほどよい刺激をもらえる
- 「一緒に頑張ろう」という連帯感が生まれる
たとえば、ランニングが趣味の人が仲間と一緒に走ったり、ギターを弾く人が動画をシェアし合ったりすることで、「ひとりではサボっていたかも」という場面でも自然と継続できるようになります。
仲間づくりの方法は多様
近年はリアルでもオンラインでも、趣味を通じたコミュニティの場が多様化しています。たとえば:
■ オンラインでのつながり
- SNS(X、Instagram、Threadsなど)で趣味アカウントを作る
- YouTubeやブログに活動記録を投稿する
- DiscordやSlackで趣味系のチャンネルに参加
- オンラインサロン・学習アプリ(語学・デザイン・手芸など)の交流機能を活用
■ リアルな場での交流
- 近所の教室・講座・ワークショップに参加する
- 公共施設や市民センターで開催される趣味サークルを探す
- カフェや図書館などのスペースでのイベント参加
- 趣味特化型のマッチングアプリや掲示板
最近は「ゆるくつながる」「無理に会話しなくてもOK」な空気感を大切にしているコミュニティも増えており、内向的な人でも安心して参加できるようになっています。
気をつけたい「仲間疲れ」
もちろん、仲間がいるからといって常に楽しいとは限りません。相手との比較で焦ってしまったり、反応がないことで落ち込んだりすることもあります。
趣味は“義務”ではなく“自分のための時間”です。以下のようなことに注意することで、心地よく関わることができます。
- 無理に発信・交流しなくていいと割り切る
- 一人でやりたいときは距離を置いてOK
- 反応がなくても自分の満足が第一
「自分のペースで関われるか?」という視点でコミュニティを選ぶと、疲れにくく、長くつながれる居場所になっていきます。
「ゆるくて楽しい」が続く鍵
大切なのは、「仲間=競争相手」ではなく、「仲間=一緒に楽しめる存在」であるというスタンスです。
SNSで自分と似た進捗の人を見つけたり、同じ教室に通う人と雑談するだけでも、「このまま続けていいんだ」と安心感を得ることができます。
また、仲間の存在は、「自分にはできないと思っていたけど、あの人も初めは初心者だった」と気づかせてくれる鏡でもあります。他人と比較するのではなく、共感や励ましをもらえる環境に身を置くことで、趣味は“ひとりの時間”から“共有できる喜び”へと変わっていきます。
3-5. 記録をとる・振り返る
趣味を長く続けるためには、「自分の進歩を実感できること」が大きな鍵になります。最初は“楽しいから”という気持ちだけで続けられたとしても、時間が経つと少しずつマンネリを感じたり、「これって意味あるのかな?」という迷いが出てきます。
そんなとき、これまでの自分の歩みを“記録”として見返せると、「ちゃんと積み重ねてきたんだ」という実感が湧き、気持ちを前向きに保つことができます。
記録とは、決して立派な日誌や作品集のようなものである必要はありません。ちょっとしたメモ、写真、チェックリストなど、小さな工夫で十分なのです。
なぜ記録が大切なのか?
人間の記憶はあいまいで、「今週どのくらい趣味に時間を使ったか」「先月どれだけ上達したか」といったことを、正確に覚えている人はほとんどいません。
だからこそ、「できたこと」「やったこと」「感じたこと」を形として残すことで、自分自身へのポジティブなフィードバックが生まれます。これが継続のエネルギーとなり、「よし、またやろう」というモチベーションを自然に引き出してくれるのです。
記録の取り方いろいろ
自分に合った記録方法を選ぶことで、負担なく、むしろ楽しく継続できます。以下に代表的な記録の方法をいくつか紹介します。
■ カレンダー・手帳にチェックをつける
- 例:「○」印をつけるだけで、達成感が得られる
- 習慣化アプリでも代用可能(Habitify、Streaks など)
■ 写真を撮って残す
- 料理、イラスト、DIYなど“成果が目に見える趣味”に最適
- スマホのアルバムを趣味専用に分けるだけでもOK
■ ノートや日記をつける
- 感じたこと、学んだこと、次回の目標などを書き残す
- 感情の整理にもつながるため、メンタル安定にも効果的
■ SNSやブログで発信する
- 自分だけの記録として非公開設定も可能
- フォロワーとのやり取りが刺激になることも
■ スプレッドシートや表で数値管理
- 語学や運動など“数値で見える進歩”がある趣味におすすめ
- 月単位での振り返りにも使いやすい
記録は「やる気がないとき」こそ効く
意外に思われるかもしれませんが、記録は“やる気が落ちたとき”にこそ効果を発揮します。「続けてきた証」が目の前にあると、「もう少しだけやってみようかな」と思えるのです。
とくにおすすめなのは、モチベーションが下がったときに過去の写真やノートを見返すこと。始めたばかりの頃と比べて「こんなに変わったんだ」「自分、結構やってるじゃん」と気づければ、それだけでやる気が復活します。
また、趣味の内容や進め方を“振り返る”ことも重要です。
「記録→振り返り→調整」のサイクルを持とう
記録はゴールではなく、継続のためのツールです。記録をただ残すだけでなく、月に1回などのタイミングで「何がうまくいったか」「何がしんどかったか」「次はどうしたいか」を振り返ると、趣味の取り組み方を改善するヒントが得られます。
この「記録→振り返り→調整」のサイクルは、仕事や学習と同じように、趣味の充実度を高める上でも非常に有効です。
3-6. 自分にやさしくなる
趣味を続けるために、意外と見落とされがちだけれどとても大切なこと。それが「自分にやさしくなること」です。これは、習慣化や行動心理学の観点からも非常に重要なポイントであり、多くの人が途中で挫折してしまうのは、この“やさしさの不足”に起因しています。
「今日はできなかった」「また三日坊主かも」「続いてる人がうらやましい」──そんなふうに、自分を責めたり否定する気持ちが強いと、趣味に対する罪悪感や自己嫌悪が生まれ、だんだんと距離ができてしまいます。
自分に厳しくしすぎると続かない
「趣味を続けたい」という思いが強い人ほど、自分に対して高い理想を持ちがちです。
- 毎日やらなきゃダメ
- 上達しなきゃ意味がない
- 人に見せられるレベルにしたい
このような“~べき思考”に縛られると、少し休んだだけで「やっぱり自分には無理だった」と感じてしまい、継続が難しくなります。
しかし、趣味は本来、結果や他人からの評価ではなく、「自分が楽しいと感じられるか」が最大の目的であるはずです。だからこそ、多少の波があっても「また始めればいい」と受け止める“やさしさ”が必要なのです。
セルフコンパッションのすすめ
心理学の世界では、「セルフコンパッション(self-compassion)」という概念があります。これは「自分に対する思いやり」「ミスや失敗をしても責めない心の態度」を指します。
セルフコンパッションが高い人は、挫折や停滞を経験しても、自分を立て直す力(レジリエンス)が強く、結果的に物事を続けやすいという研究もあります。
趣味に対してもこの考え方は非常に有効です。たとえば、
- 「今日はできなかったけど、疲れてたんだ。休むのも大事」
- 「途中で止まってたけど、また再開できた自分を褒めよう」
- 「上手くできなくても、やろうと思っただけですごい」
こうした言葉を自分にかけてあげることで、趣味へのプレッシャーが軽減され、気持ちよく再開できるようになります。
「続けること」ではなく「戻ってこれること」が大事
人間は誰しも、気分の浮き沈みや生活の変化によって、趣味に対するモチベーションが上下します。それはごく当たり前のことです。大事なのは、「毎日続けること」よりも、「やめても、また戻ってこれること」を許容できるかどうかです。
たとえば、「3ヶ月休んでたけど、またやってみた」だけでも十分すごいことです。それを「続いていない」と否定するのではなく、「戻ってきたこと」にフォーカスする──この視点を持てるだけで、趣味はもっと自由で、楽しいものになります。
自分の“ペース”を大切にする
SNSなどで「毎日やってます!」「3年続けてます!」という投稿を見ると、「自分はダメだな」と思ってしまうかもしれません。しかし、趣味において“他人のペース”はまったく参考になりません。
あなたの生活リズム、体調、気分、性格……すべてが違うのですから、比較する意味はないのです。むしろ、「自分にちょうどいいペース」で細く長く付き合えるほうが、無理なく心地よく続けられる趣味になります。
やさしさは継続のための土台になる
趣味を続けたいなら、自分に厳しくなるよりも、やさしくなることが一番の近道です。うまくいかない日があっても、自分を責めず、またやってみようと思える。その気持ちの余白が、結果として“続いている自分”をつくってくれます。
だから、今日できなかったとしても大丈夫。また明日、また来週、また来月でも。趣味はあなたのペースで、ゆっくり育てていけばいいのです。
4. 幅広い事例&アンケート声
これまでのセクションでは、趣味が続かない理由と、続けるための具体策を体系的にご紹介してきました。ここからは実際に“趣味を始めてみた人たち”のリアルな声をもとに、どのようなきっかけで趣味を始め、どんな工夫で続けているのかをご紹介します。
体験談やアンケート結果からは、机上の理論とはまた違った「現場のヒント」が見えてきます。共感できるエピソードや、新たな視点のヒントとしてぜひ参考にしてみてください。
事例①:料理(30代女性・会社員)
きっかけ:「コロナ禍で外食が減り、気分転換に始めた」
工夫:「最初はキット付きのミールセットを週に1回だけ注文。レシピ通り作って成功体験が得られた」
続けられた理由:「食べた家族の反応がうれしくて“また作ろう”と思えた。今では料理がリフレッシュ手段」
🔍ポイント:小さな成功体験とポジティブなフィードバックが継続の原動力に
事例②:イラスト(20代男性・大学生)
きっかけ:「SNSで趣味アカウントを見て“自分も描いてみたい”と思った」
工夫:「上手く描くことよりも“毎日1枚投稿する”ことを目標に。ハードルを下げて継続」
挫折しそうになった時:「他人と比べて苦しくなったが、“昨日の自分より良ければOK”という考えに切り替えた」
🔍ポイント:他人との比較から“自己成長”への視点転換が大切
事例③:ウォーキング(50代男性・自営業)
きっかけ:「健康診断で指摘されて運動を始めようと決意」
工夫:「最初は1日10分だけ歩く。記録アプリで歩数を“見える化”」
継続につながった要素:「結果より“日々の積み重ね”を意識。歩く時間が“自分と向き合う時間”に」
🔍ポイント:趣味=ルーティンと自己メンテナンスの時間として定義
事例④:カリグラフィー(40代女性・パート)
きっかけ:「SNSで見かけた美しい手書き文字に魅了されて」
最初の壁:「道具の使い方が難しく、理想と現実のギャップに挫折しかけた」
乗り越えた方法:「“毎日じゃなくてもいい”“1文字だけでもやったらOK”と自分に許可を出した」
🔍ポイント:完璧主義を手放し、“楽しむこと”を優先するマインドチェンジ
アンケート調査(n=120、当サイト調べ)
Q. 趣味が続かなくなったことはありますか?
- はい:88%
- いいえ:12%
Q. 続かなかった理由は?(複数回答可)
- 時間がなかった:62%
- 飽きた:55%
- お金がかかった:38%
- 成果が見えなかった:35%
- 他人と比べて自信をなくした:24%
Q. 趣味が続いている理由は?(継続者n=44)
- 習慣に組み込めている:66%
- 小さな目標を設定している:48%
- 一緒に楽しめる仲間がいる:39%
- 記録をとって振り返っている:32%
- 誰にも見せずに自分のペースで楽しんでいる:30%
まとめ:リアルな声が示す“続けるコツ”
実際の声からは、「頑張りすぎない」「小さく始める」「他人と比べない」「楽しさを忘れない」といった共通点が多く見られました。誰もが最初から上手くできていたわけではなく、「どう向き合うか」「どこに基準を置くか」によって、趣味の継続度合いが変わっていくのです。
5. よくあるQ&A
趣味を始めようとするとき、あるいは続けていくなかで、多くの人が共通して抱える疑問があります。このセクションでは、実際に寄せられることの多い質問をピックアップし、趣味をより前向きに楽しむためのヒントをQ&A形式でご紹介します。
Q1. 飽きっぽい性格でも、趣味は続けられますか?
A. はい、続けられます。大切なのは“飽きる前提”で設計することです。
飽きること自体は決して悪いことではありません。人間は誰しも新しい刺激を求める生き物です。そのため、1つの趣味に飽きたからといって「自分はダメだ」と思う必要はありません。
おすすめの方法は、「複数の趣味を並行して持つ」「一時的に休んでもまた戻ってこれるようにする」といった“柔軟なスタイル”を許容することです。また、同じ趣味でも角度を変えて楽しむ(例:写真→スマホからフィルムへ、料理→和食から中華へ)といった工夫も効果的です。
Q2. 毎日やらないと続かないですか?
A. いいえ。週に1回やるだけでも立派な「継続」です。
“毎日やる”というのは、あくまで理想のひとつに過ぎません。忙しい日常の中では、趣味に使える時間は限られます。だからこそ、「週末にだけやる」「月に2回だけ」といった、自分の生活スタイルに合った頻度で楽しむことが大切です。
また、趣味は「休んでもまた戻ってくればOK」です。できなかった日より、「またやってみよう」と思えたその気持ちを大切にしてください。
Q3. 趣味と仕事のバランスがとれません。どうしたらいいですか?
A. 趣味は“義務”ではなく“余白”と考えるとバランスがとりやすくなります。
仕事が忙しくなると、趣味の時間が確保できず「やらなきゃ」と思ってかえってストレスになることがあります。そんなときは、“日常の延長でできる軽い趣味”に切り替えるのがおすすめです。
たとえば、出勤前に1ページだけ読書をする、昼休みに散歩をする、寝る前に10分だけ日記を書く──など、ライフスタイルの中に溶け込む趣味を意識することで、無理なく楽しみが持てるようになります。
Q4. お金がかからない趣味ってありますか?
A. あります。無料〜低コストで始められる趣味はたくさんあります。
たとえば、
- 読書(図書館を利用すれば無料)
- 散歩・ウォーキング
https://shumisagashi.com/%e6%95%a3%e6%ad%a9%e3%82%92%e8%b6%a3%e5%91%b3%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e6%95%a3%e6%ad%a9%e3%81%ae%e8%b6%a3%e5%91%b3%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89/ - イラスト(紙とペンがあればOK)
https://shumisagashi.com/%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91%ef%bc%81%e7%b5%b5%e7%94%bb%e3%81%ae%e8%b6%a3%e5%91%b3%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9%e3%81%aa%e3%82%bb%e3%83%83/ - 写真撮影(スマホカメラで十分)
https://shumisagashi.com/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e8%b6%a3%e5%91%b3%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%81%ae%e8%b6%a3%e5%91%b3%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89/ - 筋トレやストレッチ(自宅で可能)
- ラジオやPodcastを聴く
- 手帳・ノート・日記
「初期投資が大きい=良い趣味」ではありません。むしろ、気軽に始められて生活の一部になりやすい“身近な趣味”こそ、長続きしやすい傾向があります。
Q5. 趣味を始めたいけど、何が向いているのかわかりません。
A. 「向いているか」より「やってみたいか」を基準にしてみましょう。
趣味に“適性”はあっても、“正解”はありません。大事なのは、始める前に向いているかを考えすぎるよりも、「面白そう」「ちょっとやってみたい」と感じた直感を信じることです。
最初から完璧にできなくてもまったく問題ありません。最初の一歩を気軽に踏み出してみることで、自分との相性が見えてきます。少しやってみて合わなければやめてもいい、また別のことに挑戦すればいい──そんな柔軟な気持ちで、まずは“お試し感覚”で始めてみてください。
Q6. 「趣味がない自分」に劣等感を感じます…
A. それはあなただけではありません。焦らず、自分のペースで探して大丈夫です。
「趣味がない=魅力がない」というわけでは決してありません。現代人は忙しさや情報過多の中で、「自分が本当に楽しめること」がわかりにくくなっているだけです。
まずは、ちょっと気になること、昔やっていたこと、やってみたかったことなどを“候補”としてリストアップしてみましょう。そして、1つずつ軽く体験していく中で、「これなら続けられそう」と思えるものに出会えることがあります。
6. まとめ&行動宣言
趣味が続かない──それは決してあなただけの悩みではありません。今回の記事では、その原因を8つに分類し、それぞれに対応する具体的な対策と、実際の体験談・アンケートデータを交えて、趣味と上手に向き合う方法を探ってきました。
おさらいすると、「続かない」の多くは以下のようなポイントに集約されます:
- 成長が見えないことでモチベーションが下がる
- 完璧主義や“べき思考”で自分を追い込んでしまう
- 続けづらい環境(時間・お金・場所)で始めている
- 他人と比較したり、承認欲求に縛られてしまう
- 心身のコンディションが整っていない状態で取り組む
これらはどれも、少しの意識や行動の工夫で改善が可能なものばかりです。
また、「趣味が続く人」の習慣や思考法からは、以下のようなヒントが得られました:
- 趣味を始める理由(=ディープドライバー)を明確にする
- 小さな一歩から始めて、達成感を積み重ねる
- 実行ハードルを下げ、生活の中に趣味を組み込む
- 仲間や記録を活用してモチベーションを維持する
- 自分に対してやさしくなることで、再開しやすい環境をつくる
趣味は人生の“ごほうび”です。
無理をして取り組むものでもなければ、義務のように続けるものでもありません。
だからこそ、「自分が心地よいと感じるペース」「毎回が楽しみになる状態」を目指すことが、何よりも大切です。
行動宣言:「次の一歩」は、今ここから。
ここまで読んでいただいたあなたに、最後に問いかけたいことがあります。
あなたは、何のために趣味を探していますか?
そして、どんな気持ちを得たいと思っていますか?
もし少しでも、「何か始めてみようかな」と思えたなら、それがもう“第一歩”です。
やるべきことは、たったひとつ。
「ちょっと気になることを、今日5分だけやってみる」
それで十分です。それがきっかけとなり、あなたにとっての“続けられる趣味”が見つかるかもしれません。
趣味は、あなたの人生を彩り、心を回復させ、思いもよらない新しい世界への扉を開いてくれます。その扉を開く鍵は、あなたの中にすでにあるのです。
最後に:趣味を「見つける」ではなく「育てる」という発想を
趣味は、最初からしっくりくるものではないかもしれません。
でも、少しずつ触れて、気楽に続けていくうちに、だんだんと自分になじんでいきます。
“見つける”というより、“育てていく”ものだと考えてみてください。
あなたらしい趣味との出会いが、きっとこれから始まりますように。



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48102b9b.6c6c2521.48102b9c.28a32de0/?me_id=1180385&item_id=10018377&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmitsuba%2Fcabinet%2Fnikon%2Fimgrc0110354276.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48102e29.c392a6ff.48102e2a.702000c8/?me_id=1270903&item_id=11521815&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000001213%2F4955295134342_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)